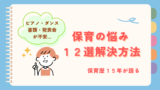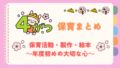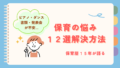今回は保育にはかかせない『シアター教材』について紹介します!
私は保育歴15年の中で、たくさんの場面で「シアター教材」を使い、子どもたちと楽しい時間を過ごしてきました。
実際にやってみて感じた、
などを紹介します!
- ペープサート
- パネルシアター
- スケッチブックシアター
- 手袋シアター
- パペットシアター
- エプロンシアター
- 大型紙芝居・絵本
保育の引き出しを増やしたい方や、新しいアイデアを探している方のヒントになれば嬉しいです♪
保育現場で役に立つ「シアタ―教材」7選紹介

最近の保育は、「保育士が主体」ではなく「子どもが主体」のスタイルへと変化してきていますね。
とはいえ、「誕生会」「お楽しみ会」「ちょっとした隙間時間」 など、保育士が出し物をする場面はまだまだ多いものです。
そんな時に大活躍するのが 「シアター教材」 です!
この記事では、使うときのコツやポイント、注意点 もあわせて紹介します。明日の保育にぜひ役立ててください。
①ペープサート

紙で作ったキャラクターを棒につけて動かしながら演じる、紙人形劇のようなシアター教材 です。
「ペープサート」の良い点
「ペープサート」の注意点と解決方法
| 注意点 | 解決方法 |
|---|---|
| キャラクターが多いと置き場所に困る | テーブルや棚が必要になります。 事前に、用意し、ペープサートも並べておくと◎ |
| 裏表の使い分けや仕掛けの準備が大変 | 作成段階から、確認しながら行えば大丈夫 |
| 慣れるまではスムーズな進行が難しいことも (ペープサートの数が多いと大変) | しっかり練習したら怖くない! |

ペープサートは、工夫次第でとても楽しくどこでも活躍する教材 になります!
②パネルシアター

布(パネル布)を貼ったボードに、フェルトや不織布で作った人形や背景を貼りながら物語を進めるシアター教材です。
「パネルシアター」の良い点
「パネルシアター」の注意点と解決方法
| 注意点 | 解決方法 |
|---|---|
| 準備に時間とコストがかかり、園によってはパネル版が無い場合も | 早めの準備と、パネル版があるか確認をする。 無い場合は、段ボールとフェルトで代用可能! |
| ボードやキャラクターがかさばるので、保管スペースが必要になる | 保管スペースも考えて、自分が利用しやすいサイズで作る。ファイルに折れないように挟んで保管が◎ |
| 楽しいストーリーが多い反面、慣れるまでは 少しハードルが高い | 練習すれば、大丈夫! |
| 大きなボードを使うため、テーブルやスタンドが必要 | 子どもに見せる場面をしっかり想定し、事前にテーブルや場所の確保をすれば◎ |
「パネルシアター」アレンジ方法

「パネル布がない!でも子どもに見せたいお話がある!」
そんなときは画用紙で代用 できます!

準備や練習に結構な時間がかかりますが、子供たちは大喜びです♪
③スケッチブックシアター
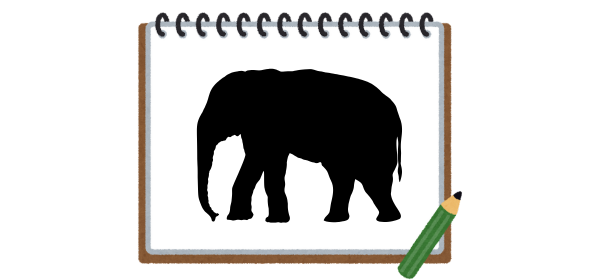
スケッチブックをめくりながらお話を進めるシアター教材。
イラストや仕掛けをつけることで、子どもたちの興味を引きやすい のが特徴です!
「スケッチブックシアター」良い点

私も、バス遠足で「スケッチブックシアター」をしました!
外で行うなら、ペープサートよりも便利です(ばらつきなし)
「スケッチブックシアター」注意点
| 注意点 | 解決方法 |
|---|---|
| イラストのセンスが問われる | 絵が苦手な場合は工夫が必要 ※下記に工夫ポイントを紹介 |
| 紙なので破れやすい | 補強したり、丁寧に扱うと◎ |
| 大人数には不向き | サイズや見せ方を工夫すると使える場合もある |
「スケッチブックシアター」の簡単ポイント
✨ 印刷したイラストを活用!
スケッチブックに手描きしなくても、印刷したイラストを貼ればOK!
この方法なら、より手軽に楽しめます♪スケッチブックシアターは、手軽さと教育効果の高さで保育現場でも大活躍!

新人さんにおすすめのシアターNO.1です。
作りやすさ、日常の保育での使いやすさ、保管のしやすさもおすすめです♪
④手袋シアタ―

手袋にフェルトや人形をつけて、お話を進めるシアター教材。手遊びと組み合わせて楽しむことも多い ですね♪
「手袋シアター」の良い点
「手袋シアター」の注意点と解決方法
| 注意点 | 解決方法 |
|---|---|
| 手芸が苦手な場合は、製作に時間がかかることも | やりたい時は、早めの準備をしましょう |
| 手袋のサイズに限りがあるため、大きな場面転換や複雑なストーリーには不向き | 題材選びに工夫すれば大丈夫! 手遊び歌や定番絵本なら相性◎ |
| 大人数には向かない(ホールなどの誕生会) | 少人数には最適!誕生会でも導入なら◎ |

手袋シアターは、小さな子どもたちと楽しく関わるのにぴったりな教材!題材選びや製作の手間を考えながら、うまく取り入れてみてください。
⑤パペットシアター

ぬいぐるみや指人形を使ってお話を展開するシアター教材。
声を変えたり、演技をつけることで、子どもたちが夢中に!
「パペットシアター」良い点
「パペットシアター」の注意点
| 注意点 | 解決方法 |
|---|---|
| 本格的に作ると、準備に時間がかかる | やろうと計画した時から、早めに準備!園にある人形で代用できるものは使用する(動物など◎) |
| 劇の題材やセリフ、BGMなど細かい準備が必要 | 事前に準備すればOK |
| 演じる力が求められる | 練習すれば大丈夫。最初から出来る人はいない! |

準備や保育士のアレンジ力も必要になりますが、子供たちが大好きです♪
大好きな人形のお話は夢中になること間違いなしです!
⑥エプロンシアター

エプロンにマジックテープやポケットをつけ、キャラクターや小物をつけたり外したりしながらお話を進めるシアター教材。
「エプロンシアター」良い点
「エプロンシアター」注意点
| 注意点 | 解決方法 |
|---|---|
| フェルトや布を使って人形や小道具を作る必要があり、材料を揃えるのがちょっと大変 | 手芸が好きな人にはぴったり |
| 台詞や歌を覚えたり、表情豊かに動いたりする必要があり、初心者には少しハードルが高い | 最初から出来る人はいない!練習と実践あるのみ |
| 大人数の前だと、後ろの子が見えにくいことも | 見やすい位置で演じたり、動きを大きくしたりと工夫するとOK |

エプロンシアターは、子どもたちのワクワク感を引き出し、想像力を育ててくれます!
是非、子供の反応を見ながら楽しんで欲しいです♪
⑦大型紙芝居・大型絵本

大きな紙に描かれた絵を順番にめくりながらお話を読む、日本の伝統的なシアター教材。
普通の紙芝居よりもサイズが大きく、特別感たっぷり!
「大型紙芝居・大型絵本」の良い点
「大型紙芝居・大型絵本」の注意点
| 注意点 | 解決方法 |
|---|---|
| ひとりで読むのはちょっと大変…大型サイズなので、めくるのにコツがいることも | 誰かと一緒にやると大丈夫! |
| サイズが大きい分、置き場所に困ることも | 図書館からレンタルしてくればOK 保育現場は広いので、置き場所は大丈夫 |
| 話し方の表現力が必要 | 読み方や間の取り方によって、お話の魅力が大きく変わるので、少し練習すると◎ |
| 見る位置によっては見えにくいことも | 子どもたちの座る位置を工夫すると、より楽しめる |

借りてきてしまえば、準備も楽で、特別感があり楽しめます!
行事の由来なども、ぴったりの絵本・紙芝居が見つかるはずです。
「シアター教材」全体として行う時のポイント

「シアター教材」を行う時のポイントは、3つあります。
1. しっかり練習しよう
道具の配置や動かし方を事前に練習して、スムーズに進行できるよう準備しましょう。
最初から完璧に出来なくても大丈夫、自分で「安心!」と思えるまで練習すると大丈夫です♪
2. 声の大きさとテンポに気をつけて
お部屋で少人数に見せる時と、ホールなど大人数の前では、声の大きさを意識して調整しましょう。
緊張すると声が小さくなりがちなので、練習で声を大きくする意識を持つと、発表の時に自然に変わりますよ!
また、緊張するとテンポが速くなることがあるので、少しゆっくり話すことを意識すると、落ち着いて進行できるはず。

練習後に他の先生に感想をもらうと、次に活かせますよ!
3. 子どもとコミュニケーションをとろう
せっかくの「シアター教材」を使った発表だから、子どもたちとコミュニケーションを取ると、より楽しい雰囲気が生まれます♪
最初は余裕がなくて難しいかもしれませんが、経験を積むと、子どもの反応を見ながら進められるようになりますよ。
無理せず、自分のペースで進んでいきましょう。
「シアター教材」無料で提供してくれるサイト
保育士さんにぴったりのイラストがたくさん提供されているサイト「ほいくえ」さんがあります。

これらの他にも、日常の保育、行事にぴったりのシアター素材を提供してくれています。
イラストも、カラー、白黒とあるので、利用しやすい方をコピーし、切り取ればOK!!
とっても便利ですので、よければ利用してみて下さい♪
まとめ
保育現場では、子どもたちが先生の「シアター」や「お話」を楽しみにしてくれます!
準備や練習は大変ですが、経験が大事です。子どもの反応を見ながら、楽しんで発表できるようになっていきます。

「自分にはこれが得意!」「これは、恥ずかしいけど、これならできそう!」
と感じるシアター教材もきっと見つかるはずです。
最初は緊張するかもしれませんが、先輩たちにもその頑張りは必ず伝わりますよ!

応援しています!がんばってください♪