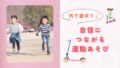トランプ、けん玉、すごろくって楽しいですよね♩

「今の子って、こういう遊びもするの?」
そんなふうに思った方にも、ぜひ知っていただきたい!
昔ながらの遊びがもつ、子どもへのすごい影響(生きる力×知育×非認知能力)について、元保育士目線でお伝えします。
スマホやゲームが当たり前になった今だからこそ、アナログな遊びが、子どもの力をぐんと引き出すことも。
この記事では、保育園で実際に子どもたちと楽しんできた中から、「これは特に子どもたちが盛り上がった!」「遊びながら学べる!」と感じたものを厳選して6つご紹介します♩
今回は、3歳以上のお子さんにおすすめの遊びをピックアップしました。
おうち時間の遊びネタとしても、ぜひ参考にしてください。
昔ながらの遊びが子どもに与える良い影響とは?

一見シンプルに見える“昔遊び”ですが、実は、子どもの発達に大切な生きる力(非認知能力)がギュッと詰まっています。
たとえば、こんな力が育ちます▼
ルールを理解して守る力(社会性・協調性)
勝ち負けを受け止める気持ちの育ち(感情のコントロール)
集中力・記憶力・思考力(学びの土台)
手先を使った巧緻性(運筆・製作・生活スキルにもつながる)
こうした力は、「あとから教えよう」と思っても、なかなか身につきません。
だからこそ――“遊びながら自然に経験する”ことがとても大切なんです。
「遊びの中から学ぶ」「非認知能力ってなに?」という方はこちらの記事もどうぞ▼
非認知能力とは?子どもの自信・集中力・やり抜く力を育てるヒント【元保育士が解説】
保育園・幼稚園でも大人気!昔ながらの遊び6選
それでは、保育園でも子どもたちに大人気だった遊びを一つずつご紹介していきます。実際の様子や、遊ぶときのポイント、遊びのアレンジ方法も交えてお届けします。
① トランプ(ばば抜き・神経衰弱など)

「えっ、もうこんなにルールを理解できるの⁉︎」と驚くくらい、子どもたちはトランプ遊びに夢中になります。
楽しく遊ぶ中で、たくさんの“育ち”が見られる遊びです。
保育現場で楽しんでいた「トランプ遊び方3選」を紹介します!
①ババ抜き
【遊びから育つ力】
【基本のルール】
- 時計回りで順番に進む
- 自分の番が来たら、隣の人の手札から1枚引く
- 同じ数字があればペアで場に捨てる(ジョーカーはペアにならない)
- 最後までカードを持っていた人が「負け」、手札が早くなくなった人が「勝ち」
【遊ぶ前に伝えたいポイント】
実はカードの仕分けが最初の難関!「同じ数字のカードは捨てていいよ〜」を、丁寧に伝えてあげてくださいね◎
小さな手にたくさんのカードを持つのは難しく、カードが多すぎると、ペアに気づけない子もいます。そんな時はヒントを出したり、一緒に確認してあげるとスムーズです♩

最初は、ババ抜き中よりも、配られたカードの仕分けの方が大変そうでした。
一緒に並べて、ペアを見つけるコツを教えてあげると、すぐに覚えて遊べるようになりますよ♩5歳(年長)頃になると、カードを配るところから子ども同士でできるようになります。
ババ抜きは、どの子にも勝てるチャンスがあるので、誰でも楽しめる遊びです♪
トランプには様々な絵柄がありますので、お子さんが興味を持ちそうなもので楽しんでみて下さい。
②しんけんすいじゃく(神経衰弱)
【遊びから育つ力】
【基本のルール】
- 順番にカードを2枚めくります
- 同じ数字のカード(例:7と7)が出たら「ペア」として自分のものに
- ペアがそろったら、もう一度続けてカードをめくってOK
- 異なるカードだったら、裏返して元の場所に戻します
- めくったカードの位置を覚えておくことがポイント!
- すべてのペアが揃うまでゲームを続け、ペアが多かった人の勝ちです
【遊びのアレンジ】
小さい子にはカードの数を少なめにして(例:1〜5だけ)遊ぶと、遊びやすくなります
トランプ以外にも「くだものカード」や「のりものカード」など、絵柄をそろえるタイプのカードもおすすめ!「同じ絵を見つけた!」という喜びが、遊びの導入にもぴったりです♪

「当てたい!覚えておきたい!」と夢中になるうちに、子どもたちはたくさんの力を育てています。
神経衰弱は、記憶力だけでなく、人との関わりや感情面の成長にもつながる遊びです♩
③ぶたのしっぽ
【遊びから育つ力】
【基本のルール】
- トランプをよく切り、すべて裏向きで円に並べます
- 順番を決めて時計回りに進みます
- 自分の番がきたら、カードを1枚引いて中央に表向きで出します
- そのカードと、すでに場に出ている一番上のカードのマークが同じだったら、場のカード全部を引き取ります
- マークが違う場合は、そのまま次の人へ
- 山札がなくなるまで繰り返し、最後にカードがいちばん少ない人が勝ち!
【遊びのアレンジ】
今回のルール(カードが少ない人が勝ち)以外に、「カードをたくさん集めた人が勝ち!」というルールでも楽しめます♩
この場合は「同じマークが出たら、山をすばやくタッチ!」としてもOK!反射神経も必要になるので、5歳以上の子どもたちにはこちらのルールが大盛り上がりでした♩

“運”と“反応”が組み合わさったおもしろさで、子どもたちが夢中になる「ぶたのしっぽ」。単純なルールの中にも、育つ力がたくさんつまっています♩
② オセロ

【遊びから育つ力】
【はじめて遊ぶときのポイント】
最初は、「ここに置いたら相手の色をひっくり返せるよ」と、挟む場所のヒントを伝えながら進めましょう
縦・横だけでなく、「斜めもひっくり返せる」というルールも少しずつ教えてあげてくださいね

静かにじっくり取り組む「オセロ」は、考える力・集中力・気持ちの調整など、たくさんの成長につながる遊びです。
ルールがシンプルだからこそ、子どもたちの“真剣なまなざし”が育っていきます♩
ひっくり返すルールになれていない子は、他のコマにぶつかってしまうので大変!!
こちらは、遊びやすいですよ♩
③ お子様将棋(どうぶつしょうぎなど)

将棋って難しそう…と思う方も多いかもしれませんが、「どうぶつしょうぎ」などは、ルールがシンプルで小さなお子さんでも楽しめます♪
【ゲームからの学び】
自然と考える力や相手を思いやる気持ちが育ちます。
大人も一緒に楽しめるので、親子時間にもぴったりですよ♪

年長担任のとき、よく子どもたちと「どうぶつしょうぎ」を楽しんでいました!ルールを覚える早さや判断力には、大人もびっくり。子どもたちの吸収力ってすごいんです…!
④ けん玉

昔からある日本の伝統的なおもちゃ「けん玉」。今でも子どもたちに大人気です!
【けん玉で育つ力】
みんなで遊べば、順番を守る・応援し合う経験も自然と育ちます。
【けん玉のポイント】
保育研修でも学びましたが、けん玉は「集中力」「思考力」「身体のコントロール」などが遊びの中でしっかり育つ、まさに“育ちの宝庫”。
\おすすめは「日本けん玉協会認定」のもの/
私もやってみて驚いたのですが、【けん玉協会認定のけん玉】バランスが少しくずれても「ピタッ」と玉が乗るんです。子供達も、大皿は簡単にのせられていました!
正しい姿勢&膝の使い方で、ぐっと成功しやすくなります。
大人なら、大皿でしたら5回あれば成功できますよ♩(私は、大皿~小皿まで出来ました!!)

「お家でも買って、たくさん遊んでます!」と言っていただけたこともあり、嬉しく思っています♪
⑤ コマ(手回しコマ)

シンプルだけど、奥が深い!回るだけで楽しいコマ遊び。
【コマで育つ力】
けん玉と同じように、たくさんの学びがつまった昔ながらの知育玩具です♪
最近はコマに触れる機会が少ないのか、保育現場ではとても集中して遊んでいました!「どっちが長く回せるかな?」と競ったり、土台を作ってコマ大会を楽しんだり…みんな夢中でした♪
私のおすすめ!子ども達が興味深く楽しんでいたコマはこちら▼

逆さコマは、勢いよく回せると、くるっと【きのこ】のようにひっくり返るので、子ども達も大はしゃぎでした♩
⑥ すごろく
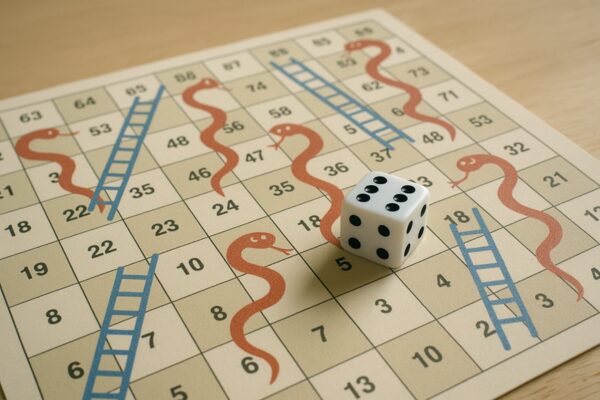
昔ながらの定番ボードゲーム「すごろく」も、実は知育効果バツグン!
【すごろくで育つ力】
【遊びのポイント】
はじめは「サイコロの数字がわからない」「進む方向をまちがえる」なんてことも。
最初は丁寧に教えて、慣れてきたら「ゴールはぴったりで!」というルールを加えると、より数に強くなりますよ!

5歳ごろになると、子どもたちだけで順番を決め、楽しんで遊ぶ姿が見られました♪オリジナルのすごろくを作って遊ぶのも盛り上がりましたよ!
家庭でも楽しもう!昔ながらの遊びとおすすめ年齢
3歳ごろなら「すごろく」や「けん玉」からスタート!
ルールがシンプルな「すごろく」や、集中力や体のバランス感覚が育つ「けん玉」は、3歳ごろのお子さんにもぴったり。
最初はうまくいかなくても、繰り返すうちにどんどん上手になっていきます。
4〜5歳になったら「トランプ」や「オセロ」にステップアップ!
年齢が上がるにつれて、少しずつ考える力やルールの理解力も育っていきます。「神経衰弱」や「ババ抜き」などのトランプゲーム、「オセロ」などもおすすめ。
ルールのある遊びで、楽しみながら集中力や戦略的思考が自然と身につきますよ。
考える遊びが好きな子には「どうぶつしょうぎ」などのお子様将棋も!
「将棋は難しそう…」という方にも人気なのが、「どうぶつしょうぎ」。動物の絵が描かれていて、コマの動かし方もシンプル。
考える力や我慢強さ、礼儀や相手を思いやる気持ちも育まれる、学びの多い遊びです。
「昔ながらの遊び」は、じわじわ楽しくなる!

最近はテレビゲームやYouTubeなど、すぐに夢中になれる遊びもたくさんありますよね。
だからこそ、昔ながらの遊びの楽しさに気づくには、ちょっと時間がかかることも。
でも、大丈夫!
最初は「難しい…」「つまらない…」という反応だった子も、2回、3回と遊ぶうちに、「できた!」「もう一回!」と夢中になっていくことが多いんです。
幼稚園・保育園での経験が、おうち遊びのきっかけに
保育園・幼稚園でも、友達同士で楽しそうに遊んでいる姿が増えると、お家でも「昔ながらの遊び」を「やりたい!!」とお話してくれているようで…

幼稚園で楽しかったから、お家でも買って遊んでます♩最近は、動画見ることが多かったのですが、家族で遊べるので嬉しいです!
保育園・幼稚園での遊びをお家でも楽しんでもらえて、とっても嬉しかったです♩

お子さんに会話に耳を傾け、子どもと一緒に楽しんでくれているお家の方にも感謝の気持ちでいっぱいでした。
まとめ|昔ながらの遊びは「育ち」の宝箱♩

テレビゲームも楽しいですが、昔ながらの遊びには、子どもたちの「育ち×生きる力(非認知能力)」に必要な力を引き出す要素がぎゅっと詰まっています。
私自身、保育士としての現場経験のなかで、子どもたちが遊びを通して「考える力」「あきらめない心」「やりきる力」など、たくさんの“生きる力(非認知能力)”を育んでいく様子を何度も見てきました。
最初は悔しくて泣いたり、最後までできなかったりしても大丈夫。
くり返し遊ぶ中で、自然と心も体もぐんぐん育っていきますよ。

保育現場でも、最初からうまくできる子はいません!
親子で、きょうだいで、お友だちと、もちろん保育園・幼稚園でも♪
ぜひ、昔ながらの遊びをおうち時間に取り入れてみてくださいね。