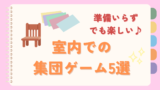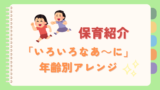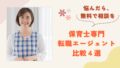こんにちは!保育歴15年の元保育士、りんです。
暖かくなり、戸外遊びが増えてきましたね。
そんな中、特に子どもたちが大好きな遊びが「おにごっこ」。

でも、年齢や月齢によって出来ることって、全然違うよね。
そんな悩みを持つ保育士さんに向けて、今回は「おすすめ おにごっこ8選」をします!
私が保育現場で、子ども達と楽しんできて、特に子供たちが夢中になっていたものを紹介します✨
- 鬼ごっこ
- 増える鬼
- 高い鬼
- 影鬼
- 手つなぎ鬼
- ドロケイ(警察と泥棒)
- 氷鬼
- しっぽ取り鬼
実際に子どもたちと遊んだ時の「こうすると楽しそうだった」「ルールの理解がスムーズだった」と感じたポイントもあわせてお伝えします。
年齢やクラスの様子に合わせて、楽しんでみてください♪
鬼ごっこのねらい・効果

鬼ごっこは、子どもたちにとって楽しい遊びであると同時に、多くの発達的な効果を持っています。
主なねらいと効果はこちらです。
1. 身体的な発達
ねらい
- 走る、止まる、方向転換するなどの動きを通じて、運動能力を高める。
- 全身を使った遊びを通じて、持久力や瞬発力を養う。
- 体幹やバランス感覚を鍛える。
効果
- 俊敏性や反射神経が向上し、転びにくくなる。
- 筋力が発達し、運動への自信がつく。
2. 社会性の向上
ねらい
- 友だちとルールを共有し、協力しながら遊ぶ力を育む。
- 勝ち負けだけでなく、相手の気持ちを考える経験をする。
- 役割を理解し、順番を守ることを学ぶ。
効果
- 友達との関わり方が上手くなり、コミュニケーション力が高まる。
- 思いやりの気持ちが芽生える。
3. 認知能力の向上
ねらい
- 鬼の動きを予測し、どう動けば捕まらないかを考える力を育む。
- 瞬時に状況を判断し、素早く行動できるようにする。
- ルールの理解力や記憶力を高める。
効果
- 判断力や問題解決能力が向上する。
- 集中力や注意力が鍛えられる。
4. 精神的な発達
ねらい
- 追いかけられるドキドキ感や逃げ切る達成感を味わう。
- 失敗しても再チャレンジする気持ちを育む。
- 運動遊びを通してストレスを発散する。
効果
- 自信がつき、挑戦する意欲が湧く。
- 遊びの中での適度な緊張感が、感情のコントロールにつながる。

鬼ごっこあそびの中から、こんなにたくさんの事を、子供たちは学んでいます✨
おすすめ おにごっこ8選

保育現場で、子供たちが楽しんでいた【人気おにごっこ】を紹介します。
遊ぶ時に、子供達がスムーズに理解できたルールの紹介、あそび方のポイントも合わせてお伝えします。
①普通の鬼ごっこ
「普通の鬼ごっこ」ルール
- 鬼を決める
- タッチされたら鬼が交代
「普通の鬼ごっこ」ポイント
鬼の帽子の色を変える
※園帽子(リバーシブル)を被って園庭遊びしている前提です。
夢中で逃げていると、誰が鬼かわからなくなりがちです。
帽子の色を変えると、逃げる子も鬼を認識しやすくなりますよ。
②増える鬼
「増える鬼」ルール
- 最初の鬼を決める
- タッチされた子も鬼になり、どんどん増えていく
- 最後は全員が鬼になり終了
「増える」ポイント
鬼になったら子は、みんな帽子の色を変える
どこに鬼がいるのか、誰を追いかければいいのかが分かりやすくなります。
途中から鬼になった子も、だれをタッチしようか…という時に迷うことなくゲームを楽しむことが出来ていました。

「増える鬼」は、ゲームの最後まで、子ども達全員が参加して楽しめるところがいですね♪
だんだん、鬼が増えてくると鬼の協力作戦がみられます。子どもたちが協力し合うところも醍醐味ですね!
③高い鬼
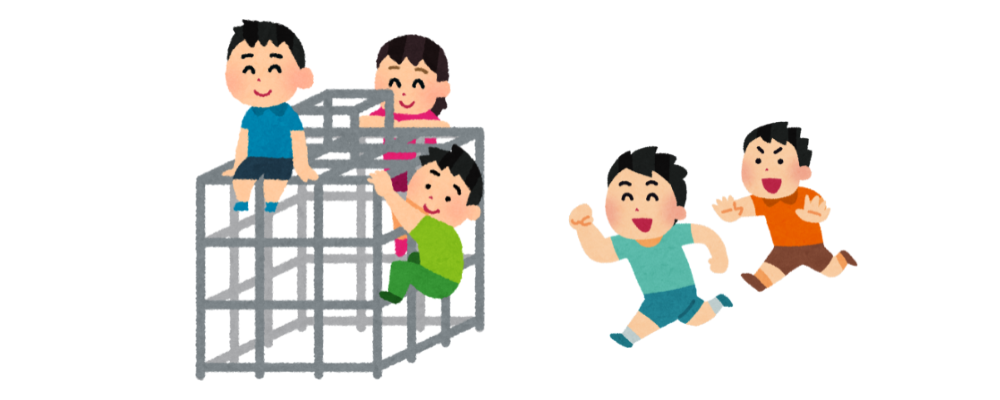
「高い鬼」ルール
- 鬼を決める
- 逃げる子は「高いところ」にいる間は鬼にタッチされない
「高い鬼」のポイント
ゲームを始める前に「高いところは5秒まで」など、ルールを決めておく
ずっと高いところにいると鬼が困ってしまいます。
事前にみんなでルールを確認すると子ども同士の理解もスムーズでしたよ。
④影鬼
「影鬼」ルール
- 鬼を決める
- 逃げる子の「影」を踏まれたら鬼と交代
「影鬼」のポイント&アレンジ
- 鬼は、帽子の色を変える
- 「増える鬼+影鬼」の組み合わせも楽しい!
だんだん鬼が増えていく影鬼。

「どうしたら皆捕まえられるか…」
「僕はこっちから!〇〇くんは、向こうから走って!!」
鬼同士が協力しながら作戦を立てる姿も見られました♪
⑤手つなぎ鬼

「手つなぎ鬼」ルール
- 鬼がタッチした子と手をつなぎ、どんどん鬼が増えていく
- 手をつないで走るため、鬼同士のチームワークが必要!
「手つなぎ鬼」ポイント
最初は保育士も鬼役をして、手をつないで走るコツを伝える
手をつないで走るのは子どもにとって意外と難しいです。
「せーの!」と声をかけたり、「長い列のときは、お友達の走る速さをみてね~」などアドバイスするとスムーズに遊べました!
⑥ドロケイ(警察と泥棒)
「ドロケイ」ルール
- 泥棒チームと警察チームに分かれる
- 警察は泥棒を捕まえて「牢屋」に入れる
- 仲間が助けに行けるルールを追加するとさらに盛り上がる
「ドロケイ」のポイント
- 鬼(警察)の帽子の色を変える
- 鬼の人数を子どもと相談して決めるのも楽しい!
はじめは鬼(警察)の人数を保育士が提案します。
(クラス20人に鬼は4人が丁度良かったです)
ゲームに慣れてきた時、鬼(警察)の人数を子どもと相談して決めることも楽しかったです。
子どもと相談すると、

「さっき、すぐに捕まえ終わったから、今回は三人にしよう」

「今回の警察役(鬼)が女の子ばかりだから、僕も鬼やるよ!今回は5人でやってみよう」
子どもたちも、友達の性格や特徴を知っています。
”子どもが考えて行う”このような遊びの中でも育まれていきますね!

年長になると話し合いが出来るようになってきます♪
⑦氷鬼
「氷鬼」ルール
- 鬼に捕まるとその場で凍る(動けなくなる)
- 味方がタッチすると復活できる
「氷鬼」アレンジ
・アレンジで「ばなな鬼ごっこ」があります!
タッチされた子が、バナナのポーズで固まります。
鬼も、仲間も誰がタッチされて固まったのかわかりやすいのがポイントです。
慣れてきたら、バナナポーズを片足で行う事も良いですよ!
待っている子もバランスを取りながらなので必死で「助けてーー!」と凍っている間も楽しいです。
⑧しっぽ取り鬼
「しっぽ取り鬼」ルール
- 逃げる子どもが腰に「しっぽ(布やテープ)」をつけ、それを鬼が取る
- 全員のしっぽを取ったら鬼交代
※鬼は2人以上が好ましいです!

「しっぽは手で押さえない事」をルールとして約束しておきましょう!
「しっぽ取り鬼」のアレンジ
鬼を決めずに、全員でのしっぽ取りも楽しいです
全員のしっぽがなくなるか、時間を決めてタイムアップで区切りをつけると行いやすいです!
はじめに、しっぽを付けてはじめる数は、ひとり一本でなく2本以上でも楽しいですよ。

- 逃げて走ることが楽しい子
- 自分のしっぽを守ることに専念する子
- 積極的にしっぽを取りに行く子
と、子どもの個性が出て面白いですよ~!!
鬼の決めかた

これらのように、鬼の決め方も沢山あります!

子どもと一緒に、考えて行ってみて下さい♪
まとめ

それぞれの鬼ごっこのルールと、遊び方のポイント・アレンジを紹介しました!
遊びの楽しいところは、年齢やクラスの特長に合わせてアレンジできることです。
鬼の人数を調整したり、「この時どうしたらいいかな?」と子どもたちと話し合いながらルールを決めるのも良いですね。
どの遊びも、柔軟に、楽しくやってみてください♪

保育士さん、保育実習生の皆さんの参考になれば嬉しいです!最後まで読んでいただき、ありがとうございました♪